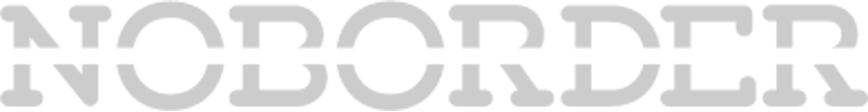「星野恭子のパラスポーツ・ピックアップ」 (154) さまざまな「記録」から振り返る、リオパラリンピック~2020東京を見据えて
低くなっていく、オリンピックとの壁
史上初めて南米で行われたリオデジャネイロ・パラリンピック。159の国と地域から4,300人以上の選手が参加し、9月7日から18日まで12日間にわたり、全22競技528種目で熱戦を展開しました。そして、世界新記録は220個、パラリンピック新記録は432個も誕生。4年前のロンドン大会に比べ、競技レベルが全体的にアップしていることを感じさせます。例えば、下肢障がい者対象のパワーリフティングではイランのラーマン選手(107kg超級)が310kgという驚異的な世界記録を樹立。健常者のベンチプレスの記録をはるかに上回る記録です。
 陸上競技場で、世界新記録誕生のたびに電光掲示板に表示された、ポルトガル語の「世界新記録」の文字。英語版表示もありまた、陸上男子1500m視覚障がいクラス(弱視)では優勝したアルジェリアのバカ選手(3分48秒29)を含む上位4人の記録が、リオ・オリンピックの金メダル記録(3分50秒00)を上回ったことも話題になりました。気象条件やレース展開などもあるので、このレースだけで「オリンピック選手を超えた」とは言えないにしても、「近づいている」のは間違いないでしょう。
陸上競技場で、世界新記録誕生のたびに電光掲示板に表示された、ポルトガル語の「世界新記録」の文字。英語版表示もありまた、陸上男子1500m視覚障がいクラス(弱視)では優勝したアルジェリアのバカ選手(3分48秒29)を含む上位4人の記録が、リオ・オリンピックの金メダル記録(3分50秒00)を上回ったことも話題になりました。気象条件やレース展開などもあるので、このレースだけで「オリンピック選手を超えた」とは言えないにしても、「近づいている」のは間違いないでしょう。
また、大会前から注目されていた右脚義足のレーム選手(ドイツ)は走り幅跳びで、オリンピックの金メダリスト越え(8m38)はなりませんでしたが、8m21の好記録で2連覇を達成。来年夏、ロンドンで開催予定の健常者と障がい者の世界陸上へのダブル出場を目指すそうです。
ロシア不在で、盤石の中国、躍進のウクライナ
メダル獲得の国別ランキングをみてみると、1位中国(239個)、2位イギリス(147個)、3位ウクライナ(117個)、4位アメリカ(115個)、5位オーストラリア(81個)。開催国ブラジルは8位(72個)でした。中国はこれで、自国開催の2008年北京大会の前、アテネ大会から4大会連続のトップとなりました。今大会は国ぐるみのドーピング問題でロシアが出場できませんでしたが、前回ロンドン大会で102個のメダルを獲得して2位に入っている強豪国です。この「ロシア分」のメダルの行方が注目されましたが、前回大会に比べ、イギリス27個、ウクライナ33個、アメリカ17個などを上積みした上位国と、29個伸ばした開催国ブラジルなどで分けあったように思います。
とはいえ、カザフスタン、ジョージア、マレーシア、ウズベキスタン、ベトナムがそれぞれ初出場以来、初めての金メダルを獲得し、ケープベルデ、モザンビーク、カタール、ウガンダは初のメダルを手にしました。少なくとも1個のメダルを獲得したのは全83カ国で、これはパラリンピック史上最大だったそうです。パラリンピックムーブメントの広がりとともに、競技力の広がりも感じさせる結果となりました。
史上初の、「金メダルゼロ」
では、「チーム日本」はどんな戦いぶりだったでしょうか。代表選手団は132選手と15名の競技パートナー147名で、17競技に出場して銀10個、銅14個の計24個のメダルを獲得しました。総数では前回ロンドン大会の16個を上回ったものの、金メダルは初出場した1964年東京大会以来、初めてゼロに終わり、ランキングも64位でした。大会前に日本が掲げた、金メダル10個、国別ランキングは10位という目標を大きく下回ったことになります。
 日本選手は手にできなかった、リオ大会の金メダルと、“金髪”仕様の大会マスコット。メダルは視覚障がい者に配慮して、振るとカラカラと音がする細工が施されたオリジナル。音色も金、銀、銅で異なる「10個」の金メダルを託された選手たちの成績はというと、例えば、陸上・走り幅跳びで世界選手権2連覇中の山本篤選手(左脚義足)は自己ベストタイの6m62を跳んだものの銀メダル。同じく昨年の世界選手権の覇者、水泳の木村敬一選手(視覚障がい・全盲)は5種目に出場し、銀2個、銅2個を獲得に留まりました。さらに、車いすテニスのエース、国枝慎吾選手は斎田悟司選手と組んだダブルスでは銅メダルでしたが、3連覇を目指したシングルスは準々決勝で敗退。ました。あと一歩まで迫りながら、取りきれなかったのです。
日本選手は手にできなかった、リオ大会の金メダルと、“金髪”仕様の大会マスコット。メダルは視覚障がい者に配慮して、振るとカラカラと音がする細工が施されたオリジナル。音色も金、銀、銅で異なる「10個」の金メダルを託された選手たちの成績はというと、例えば、陸上・走り幅跳びで世界選手権2連覇中の山本篤選手(左脚義足)は自己ベストタイの6m62を跳んだものの銀メダル。同じく昨年の世界選手権の覇者、水泳の木村敬一選手(視覚障がい・全盲)は5種目に出場し、銀2個、銅2個を獲得に留まりました。さらに、車いすテニスのエース、国枝慎吾選手は斎田悟司選手と組んだダブルスでは銅メダルでしたが、3連覇を目指したシングルスは準々決勝で敗退。ました。あと一歩まで迫りながら、取りきれなかったのです。
大槻洋也団長は大会前の目標を、「4年後の東京大会を見据え、必要な目標」と説明していましたが、大会後の解団式でも、「東京大会ではあくまでも金メダル22個、ランキング7位を目指す」とし、そのために、「各競技団体は今回の結果を客観的に分析し、強化につなげてほしい」と話していました。
とはいえ、世界的に競技レベルが上がっている今、競技団体任せの強化ではそう簡単に追いつけるものではないでしょう。メダル上位国を見ると、例えば、イギリスやアメリカは長年、「スポーツ大国」ですし、中国やウクライナは国家レベルで選手育成に取り組んでいることが知られています。素質ある選手を集め、生活を保障した上で練習に専念させる体制を整えているといわれます。
日本は1964年東京大会以来、パラリンピックへの出場を続けていますが、2013年秋に、20年東京大会開催が決まるまでは話題になることも少なく、現場も家族や関係者がボランティアベースで支えるような状態でした。
14年に障がい者スポーツの管轄が厚生労働省から文部科学省に移管され、15年にスポーツ庁が発足するなど状況はだいぶ変わってきてはいます。障がい者スポーツに配分される予算は格段に増え、オリンピック選手専用だったナショナルトレーニングセンターもパラリンピック選手の利用が可能になりました。アスリート雇用をはじめ、企業によるパラスポーツ支援も増えてきています。
東京に向けて、今こそ力の結集を
でも、まだアルバイトをしながら競技生活をつづけている選手や、育成や強化体制などが不十分な競技団体も少なくありません。配分された予算も、さまざまな要因で有意義に使いこなせていないという声も耳にします。オリンピック選手とはまだいろいろ格差があるのが実情です。山本選手は好成績のためには練習環境の充実が必要と指摘していましたが、障がい者に対する偏見などもあり、民間のスポーツジムでは利用を断わるところもあるなど自由に使えるスポーツ施設もまだ少ないのが現状です。また、練習環境とは施設のだけではありません。海外遠征や練習時間に関する勤務先の理解なども含まれるし、視覚障がい選手の練習パートナーや、移動などに介助者を必要とする競技も少なくありません。指導体制についてもまだ、ボランティアベースが一般的だし、パラ競技の専門性をもったコーチもまだ少なかったりします。選手個々の努力だけではやはり限界があります。
2020年まで、あと「4年もある」のか、「4年しかない」のか? 国として、金メダル目標を立てるなら、その目標達成をバックアップするために、国レベルでの努力も必要です。課題は満載ですが、20年東京大大会の取り組みはその先にもつながるもの。早急に、具体的な取り組みを期待したいです。 v もちろん、選手の意識改革も必要でしょう。世界を目指すアスリートとして、生活全般から見直し、自分に厳しく競技に取り組む姿勢が不可欠です。リオの結果を真摯に受け止め、リオで抱いた「悔しい思い」を糧に、今こそ「チームジャパン」の底力を発揮するときではないでしょうか。
(文・写真: 星野恭子)